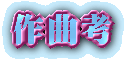
【序章】
皆様方の中にはすでに、各々の太鼓組織に於いて創作曲を作られている方がおられるかもしれません。創作しようと思っても、どこから手を着けていいものやら、さっぱりと解らないと仰る方もいるかも知れません。いえ、後者の方が断然多いはずです。私たちは、そんな方のために、作曲のページをご提供いたします。どうぞ今後の創作のプラスにしていただければ幸いに存じます。
先ず、最初にこの疑問に対してレス頂きました。
愛媛県松山市の「SHIN@心参太鼓」さんからの、ご教授を紹介いたします。◆曲を作る場合、二通りの方法があると思うのですが一つ目は曲名や喜怒哀楽といったような何を表現するかが最初に決まっていて、それを念頭におきながらリズムを起こしていくやり方。もう一つは、身体から起こるリズムを最終的に曲に結びつけるやり方。
私の場合は後者のほうが作りやすく、基本的にこちらのほうで曲が出来上がっていきます。難を言えば、行き当たりばったりでそうやって出来上がった曲が、何の意味を成しているのか突っ込まれると非常に弱いところがあります。身体のノリの部分で作っている訳ですから。
「こういうリズムが身体から出ました。」としか言いようがありません。(笑)
●【本題1】
リズムと言うのは「時間を刻むもの」と思っているので、その時その時の感情や考えている事、身体の体調、全ての事がエッセンスになってリズムが起きてくる。その時期のもろもろの情景の集大成が曲となっていくのではないかと思います。
大風呂敷を広げたような表現になってしまいましたが、日常のなんでもない時間、車の運転をしていてとか、昼飯を食べていてとか、何か考え事をしている時とか、そんな時に起きてくるリズムを書き留めていて、そういった何かの拍子に出てきたリズムをだんだんと貯めていき、後におかしくならないように数珠繋ぎにするとそれとなく曲になります。
◆曲作りの単位としては、まずベースになる地打ち。そして、地打ちにあわせてのメロディーラインになる笛やソロ打ち。ソロ打ちに幅を持たせる、裏打ち的なリズム。
この他、にぎやかさやパンチの効いたものにしようとすると、金属系の楽器ははずせなくなると思います。地打ちの部分は非常に大事で、単純なところでは「ドンドコドンドコ」とか「テンテンテンテン」などが一般的とは思いますが、4小節に渡っての地打ちもありますし、この地打ちの雰囲気によって、ソロ打ちのリズムの組み立て方が半分決まってきます。なんでもない時間に起こってくるリズムとは私の場合、こういった地打ちの部分がほとんどです。
◆作曲する時に必ず気をつけていることは、「起承転結」もしくは「序破急」です。 これは作曲に限らず、大きな意味ではステージでの演目の構成にも関わり、小さな意味では曲の中のアドリブの部分でも必要になってくる一つの演出法だと思っています。曲の良し悪しがある程度わかれるのはこの「起承転結」の転換の部分で、「起」から「承」に移ったときなどにスムーズに移れているか、移ったことが判り易いか、もう一つは「起」が「起」らしいか、など突っ込んでいくといくらでもハードルはあります。私自身の現時点はこの突っ込みがあまいので、いつも自戒しています。
◆私が曲を作るにおいての手法の一つとしては、その曲の柱になるテーマ (三宅太鼓に例えると「ドンツクドンツクドンドンツク・・・」の部分)を最初に決めておいて、これを「起」と「結」の部分に持ってきます。「起」と「結」の部分でどういう変化をつけるかは、作曲者の意図によって変化するので一概には言えませんが、曲の流れとしては尻上がりに終わるのがいいと思うので「結」の部分ではテーマを堅持しつつ或いは逆に壊しながら、見た目にも聞く耳にも賑やかなリズム構成(単純に言えば手数の多い、もしくは重低音の効いた音を多用するなど)をすると効果的になると思います。 静かな曲、情景描写の曲においてはこの限りではありませんが。
◆「承」〜「転」の部分は、いわゆる「1ソロ」「2ソロ」といった個人もしくはパートごとの「ソロ打ち」を展開していきます。 「ソロ打ち」は即興にするのもよし、そのソロを担当する人の味になってきます。作曲者としては最初から、譜面を書いて渡すよりも大体こんな感じ・・的な概要と簡単なリズムを起こしておいて、あとは担当者なりの味付けをしてもらうと、曲としての面白さが増してくるような気がします。
「ソロ打ち」の数としては、あまり多くなると各々がよほど特異なリズム或いは動きが加わらない限り、見る者にとっては飽きのくるものになってしまう気がするので、3ソロが平均、多い場合には一つのソロに充てる時間を短縮して転換をサクサクと進めるといいと思います。
◆ 「太鼓は見た目」と言うのは同感です。 これにはとても大きな意味が含まれていると思うのですが、太鼓の配置などは、ただただ置いただけでは見た目にも良くないと思いますし当然、バランスを考えた置き方、作曲の意図に応じた置き方は必要になってきますが、このほかの部分では例えば立ち姿、演奏中の姿勢、終わった後の立ち振る舞い、全て観客に見せているわけですから、一貫して気の抜けるものではありません。 演奏だけが全てではなく、観客の前に立って、台だしなどの準備の一つにもこの見た目というのは大切な要素になってくると思っています。
◆ソロのリズム作りにおいては、当然、作曲者の意図を考慮せねばなりませんが、作り方の一つのコツとしては、「スペシャルリズム」(最終的に打つサビのリズム)を一つ作っておきます。
「スペシャルリズム」の作り方は基本的に同じリズムの繰り返しになります。単純なところでは4/4で8分音符の1小節連続打ちを3回ないし4回などこの単純な連続打ちが効果的で、単純かつ見た目にも明快なリズムが説得力があるように思います。
「3回聞くと飽きる」というのはこのこととも共通してると思いますが、同じ力配分で同じことをやると飽きがきますが、一回目より二回目、二回目より三回目といったように、力配分を変えるだけで逆に見る者の目を惹きつける効果的要素となります。
「スペシャルリズム」の選定においての注意点としては、あまり細かい手を打ち過ぎると、視覚的にはおとなしくなり、音量的にも弱くなってくるので「単純明快」というのがキーワードになります。
「スペシャルリズム」がある程度、決まったら、これをソロ打ちの中の「結」の部分に持ってきます。こうしておいて「起」「承」「転」の部分を「結」が引き立つように練り上げ、組み立てていきますが難しいのはここからで、作る人の感性、手腕になってきます。 イメージとしては「魚釣り」に似ていると言う人もいます。 大切に思うのは、「波」と「呼吸」です。最初から最後まで力まかせの押せ押せのソロは、観客に息を詰めさせるばかりで、演奏者としても肉体的疲労の割には思ったほどの効果を得られないように思います。 そういった意味で、観客に息を吸わせる部分も必要になってきますし押せば引くの「力の波」も作らないと、観客、演奏者の双方が疲れます。
◆ソロ作りの一つの手法としては、序盤では、まず最初に他を押しのけてソロをする訳ですから「私を見て!」的なアピールをせねばなりません。 リズム的には「結」に近い単純明快なものがいいと思いますし、力配分的においてはフルパワーに近い方が目にとまりやすくなります。 中盤においては、既に観客の目はこちらに向いていますからあまりガンガン打たずに、飽きさせないリズム転換をしながら徐々に「結」に向かっての誘いをします。 (この部分が釣りに似てるかもしれません。) そして最後が「スペシャルリズム」となりますが、最初に決めてたスペシャルリズムが、これまでの経緯によって変化する事もあります。いずれにせよ、「力はフルパワー、リズムは単純明快」ということには変わりありません。
●「転」
◆「起承転結」の中で一番難しいのは、もしかしたら「転」の部分かもしれません。
曲中のスパイス的な役割を果たし、「起、承」で積み上げてきた雰囲気を一変しまたは、よりパンチの効いたものに束ねて、次の「結」が最高に引き立つような誘いが望まれます。また、曲全体の面白みの部分を担っているような気がします。
「こーなって、あーなって、だから、こうなったのよ」の中の「だから」の部分なのでそれなりに説得力も必要になってくると思います。
抽象的な言いまわしになりましたが、「転」は基本的に短いように思います。私がよく使うのは、無音、いわゆる4拍ブレイクなどがありますが、「転」の部分に「テーマ」を持ってくることもありますし、いずれにせよ、最高の「結」=「ゴール」をするための最終準備ですから、そういう観点でリズム作りをします。
●「作曲機器について」
◆曲がある程度出来上がったら、実際の出来上がり具合を耳にしたいものです。今までは、メンバーに曲を憶えてもらった上での合奏や、1パートごとに録音をして重ねていく多重録音をしたテープを聞いたりと、とても時間のかかる作業でしたが、最近になってDTM、シーケンサー、サイレントドラムといった 電子機器、楽器またはソフトが巷に出回っています。高いものは10万円程度、ソフトに至っては2、3万円で入手できます。私が使っているのはYAMAHA製のものですが、ソフトなどは楽譜形式で入力したものを音にも出せるし、楽譜をプリントアウト(多少の制約はありますが)もできるのでとても重宝しています。ただ、最初のとっつきが悪く、音楽入力の概念を学ぶのに思わぬ時間がかかった記憶があります。
ちなみに私の使っている機器およびソフトは、DTX(サイレントドラム)、QY70(シーケンサー)、XG Works (アプリケーションソフト)です。全て、ヤマハ製です。お互いに互換性があるので、どうしても同じメーカーになってしまいます。(メーカーの戦略にはまっている私。)
●「あとがき」
◆以上、色々と長々と、作曲について書いてきましたが、作曲をするにあたって当然の如く「絶対の方法」などはあり得ないと思っています。
全ては、作曲者または演奏者の『感性』に頼るところが非常に大きく、私としては、とりあえずの枠をこしらえて、枠の中を埋めていく作業は自分、或いはメンバーに任せっきりかもしれません。曲が出来たからゴールではなくて、そこからが新たなスタートであり時を経ること、演奏者が変わることで変化し、進化?し、曲としてより良い方向に 成長してくれればいいなあと他人事のようですが、そんな風に常々思っています。最後に、こういった考えを活字にする機会を与えてくださったゲインさん、設問していただいた方に感謝します。長々と読んでいただき有難う御座いました。 <完>
宮城県仙台市の「AKEMI@加茂綱村太鼓」さんからのご教授を、紹介いたします。
◆私は、作曲するときまずベースとなるリズム(テッケテッケとかテッテケテッテケとか)を決めます。
その次にメロディの音階を考えます。4度音程の積み重ね方でいろいろな民族的な特徴がでてくると思っているので、その曲のイメージに合った音階を作ってしまうのです。あとは、音階に当てはめながら思いつくままメロディをつなげます。 そして、メロディに合ったリズムを加えます。音階を作っておくと、2重奏が楽に作れます。
『加茂綱村囃子』は、ABACAという形で、Aがテーマ、笛のメロディは変わらないのですが、3回目のAは、テンポも早くリズムも細かくなってます。
Bは、組太鼓と宮太鼓の掛け合い、Cは、笛の二重奏から静かに始まって、締太鼓・桶胴太鼓・宮太鼓のオロシ(これが好きなのです。)の掛け合いに能管を加え、3回目のAになだれ込みます。オロシは、一人一人の個性がでてきておもしろいです。
同じフレーズは、3回目には変化させると良い、と聞いたことがあります。2回では印象に残らず、4回では飽きる。何でも3回がポイントかも。
ソロ打ちは個人に任せた方が、一番得意なパターンを叩いてもらえると思うのですが、全体のバランスや個人の力量も考えなければならないので難しいです。何よりも聞かせ所ですもん。
太鼓の配置を工夫してみるのもひとつの方法だと思います。たとえ4回同じフレーズが続いても、太鼓の種類や配置の工夫で見てる人には、飽きないことも。『太鼓は、見た目』がすごく影響すると、思います。
●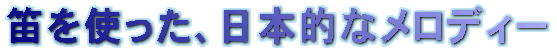
★メロディーが思うように続かない。
★笛を2本使いたいが、うまくハモれない。
このようなことはありませんか?
日本的なメロディーを作りたい、西洋音楽とは違うハモリを出したい時など、使いたい音階を決めてしまうのも一つの方法だと思います。
◆メロディー作りの参考に、日本の音階の作り方の例をご紹介したいと思います。
【4つのテトラコルド】(開始音をド<ハ>にしてます)
1.都節<みやこぶし>のテトラコルド。
2.律のテトラコルド。
3.民謡のテトラコルド。
4.琉球のテトラコルド。
例えば、都節のテトラコルドを2つ積み重ねると。
という都節の音階ができます。
また、次のように都節と民謡のテトラコルドを積み重ねると
という音階もできます。積み重ね方で、イメージに合った音階ができたら、使いたい笛などに合わせ移調します。
笛の二重奏も音階にあてはめると民族的な響きになります。
日本は縦に長い国です。同じ歌でも歌い継がれていくうちに音階が変わってしまうこともあるようです。
「ずいずいずっころばし」
A はド レ ファ ソ ラ ド (律の音階)
Bはド bレ ファ ソ bラ ド (都節の音階)
どちらで歌ってますか。
創作太鼓の中で、笛を使ったメロディー作りの参考になればと思います。
各地で、いろいろな創作曲が誕生すれば、うれしいです。
◎Akemi@加茂綱村太鼓さんの笛に関する太鼓考でした。
ていねいな、解説に非常に参考になりました。ありがとうございました。