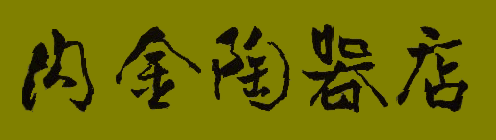三重県伊賀の地は、焼きものに適した良質の陶土に恵まれ、 桃山時代には、茶の湯とのかかわりの中で独特で豪壮な風格を確立させました。
「破調の美」として「箆目(へらめ)の作意」「耳や擂座(るいざ)のデザインバランス」「焦げ」「火色」
「歪みやひび割れ、灰や飛び散る破片」そして「きらめくような美しさが生まれるビードロ釉の烈しい炎の洗礼」
という特色を形成しています。
俗に「伊賀の七度焼」と呼ばれるように高温で長時間焼成し、
陶土からにじみでたガラス成分が松の灰や煙と融合して自然釉のビードロが生まれ、
他に類例を見ることができないほどの破格の美をかもしだしています。
松尾芭蕉も愛した「侘び」の世界の中にこのような壮絶な造形理念が、
大自然の変化をくぐりぬけて生き続けているのです。
伊賀焼の特徴
破格の美・破調の美
伊賀焼の伝統美には、あえて基本を崩し造形の極致を生み出す古伊賀の「破格の美」の存在があります。
桃山時代、伊賀領主・筒井定次は、古田織部の指導を得て、中世の伊賀焼とは異なる豪壮な織部好みの「筒井伊賀」を生み出しました。
江戸時代、藤堂高虎に替わった後は、「藤堂伊賀」が作られ、その後、小堀遠州により「遠州伊賀」が作られ、
これらを一般に「古伊賀」と呼ばれています。
現在、東京五島美術館に収蔵されている銘「破袋(やぶれぶくろ)」の耳付水指は、最高峰の逸品です。
伊賀の七度焼
何回も何日も焼成した伊賀焼を比喩しています。伊賀の粘土は同じ作品を何度も焼くことにより、
「釉」「焦げ」「火色」を表現します。
耳(みみ)
「伊賀に耳あり」といわれ、桃山時代から江戸時代初期の古伊賀の茶陶の造形感を象徴するものです。
古伊賀の水指や花入れには耳付きが多いのが特徴です。

蜻蛉の目(とんぼのめ)
自然釉が高温で焼き〆られ融けて筋状に流れ、丸い半球状になった釉溜まりのことをいいます。
自然釉の蜻蛉の目はとても美しく、茶人たちはその景色を楽しみました。

火色(ひいろ)
伊賀の土は鉄分が少なく、焼成することにより、塩分・水分・降灰などの条件が反応し、土肌がほんのり赤っぽく発色します。

ビードロ釉(びーどろゆう)・自然釉(しぜんゆう)
焼成温度が1250℃〜1300℃前後になると、降りかかったアカマツの灰が素地中の長石と共に融けてガラス質の釉となって流れ出し、
自然降灰の量と焼成具合で、萌黄色から鮮緑色まで美しく変化します。

焦げ(こげ)
窯の焚き口近くに置かれ、薪の灰が降りかかると、その部分は炭素を含んで強い還元状態になり、肌に焦げを生じ、
灰の掛かり具合で、褐色や黒褐色に変わります。

箆目(へらめ)
大胆な縦箆、横箆を使い、より荒々しくダイナミックに強いアクセントをつけています。

擂座(るいざ)
口周りにある6個の丸い浮き文を現し、伊賀焼水指の代表的な作振りです。