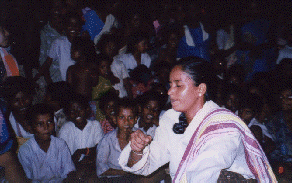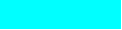Vol.2
いよいよ民衆劇のはじまり。差別と搾取の長い歴史の中で、「怒り」の感情さえも奪われてきた民衆が劇を通して「意識化」していく。「地主による搾取と抑圧」「役人たちの不正の実態」「家庭での女性たちの過酷な状況」などを劇の中で演じて見せることによって、観衆はその劇の中に自分たちの生活や姿を重ねる。そして、その現状を変革していくための「闘い」を動機づけられるのだ。
民衆劇は「アニメーションシアター」とも呼ばれ、劇を演じた者(アニメーター)が
観衆一人ひとりに問題を投げかける。
「この夫の暴力に泣いている女性が、もしあなたの娘だったら?・・・」と対話を始める。観衆とのやりとりの中で、自分の現実に置き換えて意識化する。これまでは「宿命」としてあきらめるしかないという「沈黙の文化」に封じ込められてきた人々を、「内側」から動かす(アニメーション)ためにこの「民衆劇」が行われる。
このような取り組みが、1980年よりインド各地で始まった。ここ南インドのアンバッカム村では、
ARP(Asosiation for the Rural Poor:農村貧困者のための協会)センターを中心に取り組みが進められている。ARPはガンジーの非暴力の方法論を用いながら、インド憲法起草者、「ダリット解放運動の父」と呼ばれるアンベードカルの思想とパウロフレイレの教育思想を重要視している。
これが民衆劇