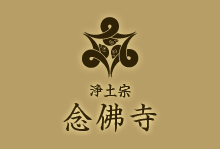子安観音堂





その形から通称『六角堂』とも呼ばれ、お檀家の皆さまのみならず、広く有信の方々からお参りいただいています。堂内中央の御厨子の中には、本堂側に子安観音菩薩をお祀りし、通用門側には聖観音菩薩をお祀りしています。御厨子の扉は普段は閉ざされており、子安観音菩薩の前には同形の子安観音菩薩を、聖観音菩薩の前には千手観音菩薩を、それぞれ御前立ちとしてお祀りしています。
子安観音菩薩は、小夜の中山(静岡県南部)にあるコユミという所から遷された御仏像とされ、その由緒は入口の上の扁額に記されています。
また御厨子の周りを囲みながら居並んでおられるのは、西国三十三ヶ所・坂東三十三ヶ所・秩父三十四ヶ所の観音霊場に由来する百体観音菩薩です。聖観音のほか、千手観音・如意輪観音・十一面観音・不空羂索観音・准胝観音・馬頭観音などの変化観音をお祀りしています。
毎月17日に『観音講』の皆さまにお勤めをいただいています。
子安(こやす)観音菩薩

子育観音、子持観音、慈母観音、持児観音などといった異称を持ち、安産や子どもの健やかな成長を願う人々に信仰されております。一般に像容としては子どもを抱く菩薩像や、子どもに乳を含ませる姿が多く、他所では幼児を抱く姿からキリストを抱く聖母マリアになぞらえ「マリア観音」と呼ばれ、隠れ切支丹の遺物と伝えられている像なども存在するそうです。
聖(しょう)観音菩薩(正観音菩薩とも)

『観音経』では、観音菩薩は人々を救うために時や処や相手に応じて三十三に姿を変えると説かれています。観音菩薩は額の上や宝冠の正面などに阿弥陀仏の化仏(けぶつ)を戴くのが特徴です。弥陀三尊で阿弥陀仏の脇侍として祀られている場合は両手で蓮座(れんざ)を身体の前に捧げる姿が多く、観音菩薩一尊で祀られる場合は、蓮の蕾や水瓶を持つ例が多いようです。
如意輪(にょいりん)観音菩薩

如意宝珠の功徳によって六道の衆生の苦を抜き、福徳智慧を得て慈悲心が増し、人々を救うことができるという出世間の利益と、富貴資財勢力威徳を全て得るという在世間の利益を与えてくれるとされています。多くの腕を持つ像と、二本の腕のみの像があり、いずれの場合も一本の肘を膝についてその手先を頬に触れるのが特徴です。
千手(せんじゅ)観音菩薩

千の手と、その掌に千の眼をそなえます。千とは無限を示す数でもあり、究極の象徴である数の手は多くの苦しみ悩む人々を観音菩薩の不可思議な力で救いとるためのもの。本来は中央の合掌する二手の他に千手を有するようですが、彫刻像では四十手をそなえ一手が二十五の衆生を済度するものとすることが多いそうです。
准胝(じゅんでい)観音菩薩

全ての菩薩の母ともいわれ、准胝仏母(ぶつも)、七具胝(しちぐてい)仏母などとも呼ばれます。具胝とは千万あるいは億を指す古代インドの数の単位で、七具胝は無量無限大を意味します。未来に生まれる衆生を哀れまれて、過去の無数の如来たちが悟りを得るために称えて験があった『仏母准胝陀羅尼(だらに)』を説くとされます。像容では持物に斧があるのが特徴です。
十一面観音菩薩

頭上に幾つもの顔を戴く観音菩薩です。財物衣服が満ち足り、病気や刀杖火水の難をまぬがれる十種勝利という現世利益と、命が終わる時に諸仏とめぐり会い、地獄へ堕ちず浄土へ往生できるという四種類の来世の果報を授けてくれるとされます。あらゆる方角『十方』に顔を向けるという観音の特性を具象化しているとも言われています。
馬頭(ばとう)観音菩薩

頭上に馬頭を戴く姿から、このように呼ばれます。憤怒の相で様々の魔障を砕き、日輪となって衆生の闇を照らし、悪趣の苦悩を断つことを本願とします。古代インドでは悪蛇を退治したり太陽の車を動かすという馬神信仰があり、この観音の成立に影響を及ぼしていると考えられています。その姿から家畜の守り神として信仰されることもあるようです。