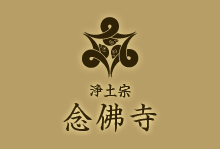阿彌陀如來坐像 解説
三重 念佛寺 藏

本像は螺髪衲衣の半丈六で、上品下生の印相を作り、右足を上にし結跏趺坐してゐる。端巌圓滿な相貌のうち、二重瞼を俯眼にし、脣邊の兩端下に窪みを有するので、一種の寂相を漾はしてゐる。頸は比較的細く兩肩を稍ゝ落し、胸腹の肉付が柔賦感を止め、兩掌や兩足の表現また寫実の妙諦を示して居り、衣紋の刻法が淺くて流麗であるのは、定朝様式の流を汲むものゝ手によって造顯されたものであらう。
本像を細視すれば、肉髻も白毫も共に水晶體になり、肉髻の奥に朱が點ぜられ、瞳に焦墨、その周に朱と胡粉を施し、脣に朱を彩してゐる。而して額の上端兩耳の一部、頸や兩腕の下部に漆箔の金地がわづかに殘存してゐるが、肉身の大部分は木肌を露はし殊に面貌は黒光してゐる。材は檜、寄木造の漆箔にして、箔の剥落した前面一帶に無数の蟲孔が存してゐる。鼻先に極少の傷、右頬に小圓形の木片の嵌入があり、左掌の中指先が欠損し、左肩より左側に垂れた衣の一部が後補になるのであるが、慈悲忍辱の彌陀の姿相が完備してゐるので、拝する者皆に敬虔な念を起さしむ。
本像の製作期に関しては、在銘もなく寺傳も詳らかでないので、確定的の言は謹みたいと思ふが、一にその造像形式により次の如く推定することが出來る。即ち本像は本寺と程遠からぬ佛土寺所藏の阿彌陀如來坐像にその像容の近似點を見出す。佛土寺の同像は承安二年「皇紀一八三二」の胎内墨書銘を有し、同じく定朝様式末流の作域を有するものである。而して当念佛寺本尊はその像容全體として、既記する如く定朝末流の形式になるが、螺髪の手法など稍ゝ荒く太目で、その一部に來るべき時代の様相がほのかに窺はれるのである。藤原時代の盛期、七條佛所によって完成された造佛の一規範も、時代の經つと共に様式の波の起伏が、次第に幽かになってわづかにその餘韻を止めるにすぎなくなり、やがて次時代の新興様式が未明の光の如く漸く影さして來る。本像の如きはその作例の一に数ふべきものか。従ってその製作期に就て、藤末鎌初の頃と推定して大過なからうと思う。