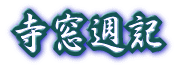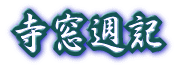| 2010年3月16日(火) |
| 紅梅が満開となりました。そして、スイセンも開花の準備に入っています。 |
|
桜の開花を始め、春たけなわの季節が待ち遠しい時節となりました。北半球中緯度に位置するこの島国では、四季が着実に訪れるということが自然の彩りと豊かさを為し、私たち日本人の五感(五官)をこれまで潤(うる)わせてくれて来たように思います。
鳩山首相が、先の国会冒頭の『所信表明演説』で「いのち」という言葉を何とのべ24回も発せられたことが話題を呼びましたが、ことほどさように、乾ききった人の心に起因する殺伐としたニュースに接する機会が多くなりました。熊本県の例の赤ちゃんポストには親達が名前も告げずに投函(?)した事例が昨年末に数10件もあったとか、また、愛知県岡崎市内のスーパーでは、カートの中に冷凍状態で2人の赤ちゃんが捨て置かれていました。昔の連続TVドラマ「おしん」の頃の貧困の時代でさえ、あり得なかったことが今日、世界有数の経済大国・長寿国を誇るこの日本で不幸なことに連日のように起きています。
昨今の『いのちブーム』には、どこか“かけ声先行”の感が否めないのは決して私一人だけではないと思います。約2500年前に仏教を開かれたインド人のお釈迦さまの『いのち観』は、私どもが人間としての命を授かったこと自体に希少な価値があると見定めることから始まっています。そして、それぞれの命が、一瞬たりとも立ち止まることを許されないこの無常の世にあって、天地の恵みと人々の労に支えられて育まれてきたことに感謝し、しっかり生きよ!と仰られています。科学の進歩によって、この世に存在するあらゆる生き物の命が根源的には同質であること(DNA等)が明らかになった今、上記のような観点からも『人としてのいのちの尊さ』ということがもっと自覚されるべきなのではないでしょうか。
当コラムを「寺窓週記」と銘打ち、駄文を連載し続けて早4年が過ぎました。今後も、微力ながら住職としての努力を続けなければならないことはもちろんですが、このあたりでいったん休刊させていただき、また、お寺の窓を通じて新しい風を入れねばと思う次第です。長きに亘りご高覧賜り本当に有り難うございました。
|
 |
 |
|
|
|
|
| 2010年2月14日(日) |
| 本堂脇間に掲げたシャカ涅槃図です。 |
|
明日2月15日は、降誕会(4/8)成道会(12/8)と並んでお釈迦さまの重要なメモリアルデーの一つである涅槃会(ねはんえ)法要の日です。2千数百年前のこの満月の夜に、お釈迦さまはガンジス川ほとりの町クシナガラにて、80歳の尊きご生涯を閉じられました。その事実はおシャカさまがいよいよ涅槃(ニルバーナ;人としての煩悩の火を吹き消された迷いのなくなった完全な悟りの境地)の世界に入られた事をも意味します。長きご生涯にわたってさまざまな人々の人柄や能力に合わせ、八万四千の法門と呼ばれるほど数多くの教えを迷いの世界に苦悩する私どものために示し続けられたお釈迦さまの最後のお姿なのです。
写真が小さ過ぎて見えないと思いますが、じっとお釈迦さまの死を見つめている弟子や菩薩たちの姿を図中から拝すると、身体を大地に打ちつけて悲嘆にくれている人や絶望のどん底に陥っていると思われる人など、一人ひとりに違う悲しみの表情を見て取れます。そして人間ばかりでなく動物たちまでもが偉大な聖者とのお別れを悲しんでいます。実はこの情景こそが今もなお私ども仏教徒の葬儀前夜の際に行われているお通夜の原点なのです。中央で金色に輝くおシャカ様のお姿が10数人分の身体ほど大きいことにお気づきかと思います。シンボリックな表現とは言え、彼らの心象としてお釈迦さまはそれほどまでに大きく映ったのでしょう。
東南アジアのタイを訪れた方のお話ですが、現地では金色に輝く巨大(全長10数m大の)な涅槃仏を拝見できるそうです。おそらく、彼の地の仏師たちにもお釈迦さまはそれほどまでに偉大に感じ取られたのでしょう。もちろん、現在の私もそのようにお釈迦さまを仰いでいる一人です。
また、この絵の裏書には「慶應二丙寅年二月十五日 総檀中」とあります。慶應年間と言えば今から約150年前、国内では百姓一揆が頻発し、やがて倒幕運動を経て江戸幕府の崩壊につながる混乱期でした。国中が疲弊したあの時代に、これほどまでに立派な絵画を寄進された当時の人々の敬虔な信仰心とその心意気にはいつもながら感心させられます。
|
 |
 |
|
|
| 2010年2月2日(火) |
| 立春を前にして雪化粧となりました。 |
|
暦の上では立春が目の前ですが、一昨年同様に昨夜から雪が降り、今朝の私の仕事は「参道の雪掻き」から始まりました。昨秋に発表された気象庁の長期予報も幾分外れがちのようで、この冬はどうも北極圏の寒気団が日本を含む地球の中緯度地帯にしばしば下りて来ているようですね。
徳永寺裏山斜面で小雪が舞う中、赤い実を鈴なりに付けたクロガネモチの木々です。写真では見えないと思いますが、葉の間では撮影中も数え切れないほどたくさんのヒヨ鳥がそれらの実をついばんでいました。
写真下は、樹齢4.5百年は経っているのでしょうか、現在は地上から(写真右下部)鉄パイプ状の梯子をあてて、かろうじて幹が皮一枚という感じで生き残っているカシの木です。徳永寺の歴史を一番知っている木かも知れません。そしてこのように老いた姿になっても、「年年歳歳花相似たり」のことわざ通り、毎年、立春の頃になるとまた枝先にたくさんの葉を茂らせ、その間に白い小さな実をこれまたたくさん付けます。自然の生命力の逞しさや不思議さには改めて驚くばかりです。と同時に、梅雨や秋の台風時にも耐えて少しでも長く私どもを楽しませてほしいと今年も願いました。
明日は春の節分です。寺の庫裏でも「福は内、鬼は外」と恒例の豆まきを行います。深い霧の中での混迷からなかなか抜け出しきれないでいる政治や経済ですが、何とか、この樫の木のような底力を発揮して私たちに明るい世界を実現してほしいものです。
|
 |
 |
|
|
| 2010年1月15日(金) |
| 「世間虚仮 唯仏是真」 |
|
いきなり難しそうな語句を紹介して恐れ入ります。いったい、何と読むのか?とお思いかも知れませんが、千数百年前に歴史上活躍された聖徳太子のお言葉で「せけんこけ ゆいぶつぜしん」と読みます。高校日本史の教科書には必ず登場している語句です。
実は、この言葉は仏教の核心を突く「教え」の一つだと思うので新年にあたりご紹介させていただきました。その意味は『この世の現象や事物は、さまざまな条件・原因によって実体を持たずに仮に存在しており(仮有)<けう>、ただ唯一、仏の教えのみが真実』ということになるようです。−岩波仏教辞典ー
つまり、この世に自分の内外に起きるさまざまな事がらを私たちは確かなものと信じて(あるいは信じたいと思って)生きているのですが、それはあくまで仮のものだということです。より具体的に言えば、この世のありとあらゆるものは(自らの身体はもちろんのこと、家族、人の心、人間組織、そして自然界に至るまで)すべてこの法則を前提に仮にバランスを保って成り立っているということです。この事は、仏教語としては一般に無我とか縁起とも解釈されますが、無常とともにシャカの教えの重要なポイントでもあります。
この点で今日の世間を見た時、地殻変動による地震も、過剰なストレスによる病気、放漫な企業経営による会社倒産、景気循環に伴う経済不況、金とモノに揺らぐ人間関係等々もすべてこの原理の中で起きていることを誰も否定できないのではないでしょうか。
以前にもこの欄で申しましたが、あの痛ましい阪神大震災の前日の16日、私は神戸市内のホテルの宴会場で教師時代の教え子の結婚披露宴の席にいました。深夜に伊賀に帰宅し朝になって地震の報道に接した時、真っ先に思案したのは新郎新婦のことでした。そして、1週間後ペットボトルの水を背負って見舞いに訪れた親戚(神戸市東灘区)の浄土宗寺院では山門と庫裏1階が全壊し、本堂と信徒会館には被災者があふれていました。
あれから15年、彼ら2人の長女もこの春には高校受験とのこと。地域にまだまだ課題は多く残っているのでしょうが、ひとまず復旧できたことを共に喜びたいと思います。地震そのものは「神様のいじわる」などではなく(そう思わざるを得ない気持ちも解らないことはないのですが)、地球が仮の存在だからこそ、このような酷(むご)い事が起きたのでしょう。また別の地でこれからもあるかも知れません。諸行無常は宇宙の哲理でもあります。だからこそ、さまざまな事態を想定に入れた緊張関係の中に自己を置き、謙虚に生きることが少しでも唯仏是真の境地につながるものと確信する一人です。
|
|
|
|
|
| 2010年1月1日(金) |
| 明けまして おめでとうございます! |
|
新しい年を迎えることになりました。旧年中は何かと一方ならぬお世話を賜り誠にありがとうございました。皆さま方各位の一層のご多幸とご健康をご祈念申し上げます。
昨夜の大晦日には、恒例の「除夜の鐘」を無事勤め上げることができました。この冬一番の冷え込みでしたので実際どれくらい参加されるのか心配でしたが、あの凍てつくような寒さにもかかわらず、檀家内外の百名を超える方々が参加され鐘を撞いていただきました。特に今年は「番号札」をお配りし、福引きをやってみました。写真上はそのうちの住職賞です。(檀家のある方が提供された)当山の寺号と紋シールが貼られた赤ワインです。この61という数字はおかげさまで還暦を迎えた私の数え年です。そして、副賞はある書家さんに書いてもらった小さな額ですが、文字は「彼女を待つのも楽しい時間」とあります。70歳代の総代さん達が選んでくれましたが、なかなか粋でしょう。
今年の干支の虎という動物は獅子と並んで怖そうでいて、顔がどことなくひょうきんなためか、昔からいろいろとことわざなどに利用されやすいようです。私などはまったくこれと逆で、顔は一見真面目そうだけど心は飼い猫みたいにおとなしく、いたって怠け者です。でも、虎のイメージを一新したのは何と言っても映画「寅さん」ですね。今となっては、あの「それを言ってしまえばおしめいよ。」の名セリフが懐かしいです。あの映画には私たち日本人の原風景が常にありましたね。
境内の鐘楼堂傍らの土塀内側に、一昨年移植した蝋梅(ろうばい)が今この寒さの中で初めて黄色い透き通るような花びらを咲かせています。低迷し続けるばかりの日本経済ですが、こちらも何とか泥沼から脱却して活力を再現させてほしいものです。皆さま本年もよろしく!
|
 |
 |
|
|
| 2009年12月15日(火) |
| 除夜の鐘つきー百八の煩悩と共に生きる私たちー |
|
あと2週間もすると、今年も大晦日を迎えます。寺院の年末はそうじや正月準備で大変忙しいですが、当山のハイライトは何と言っても、やはり「除夜の鐘」撞きです。毎年、大勢の方が参加され賑わいます。もちろん、撞かれた直後に一人ひとりに住職として新年のご挨拶をさせていただきますが、特に、小さいお子さん連れやご夫婦の方々に接する際には心が和みます。今年は福引も行う予定です。
ところで、除夜の鐘はどうして百八回撞くのかご存知ですか?ふつう、人間が持っている煩悩の数だとよく言われますが、どうしてそれが百八つものたくさんになるのかという点です。いくつかの説があるのですが、今回は代表的なものを少し説明させていただくことにします。
私ども人間はおそらく動物の中でも最も煩悩(ぼんのう)が多いかと思います。それというのは、人間の「眼・耳・鼻・舌・身・意」という6つの感覚器官がそれぞれ行う快感(楽)不快感(苦)どちらでもない(捨)という3種の感受と、さらには好・悪・平(どちらでもない)という3種の評価、つまり6種類の感覚パターンに起因すると言われています。まずはここまでで6×6計36個になるかと思いますが、これらの感受作用を日ごろ私たちは無意識の内に行っているというのです。このうち人間の場合は特に複雑で高等なのが「意識」であり、その結果、喜びも感動もそして悩みも他に比べ格段に多くなるということです。
でもその一方で、人間がこれほどまでに発達し続けたということもまぎれの無い事実ですね。
この煩悩とは、生まれる前の過去世から今の現在世を越えて未来世にわたるまでつき合うということですから、36×3で計108個となります。いずれにしても、三世(さんぜ)という、とてつも長い時間軸と心の奥底までを広く眺めての感情の数と思ったら間違いありません。
したがって、自身の中にある百八の煩悩を除夜の「鐘の音」によってさ(覚)ますとお考えになってはいかがでしょうか。そして、これらの煩悩を超えた世界こそが、私たちが仰ぐ「仏の世界」とお思いください。
|
 |
 |
|
|
| 2009年12月1日(火) |
| 今年も、いよいよ師走です。 |
|
先週は、全国的に冷え込みが厳しかったですが、今日あたりはどこか小春日和の感じさえする気候だったので境内周辺の写真を2枚撮りました。どちら様もそうだと思うのですが、カレンダーをめくるといよいよ最後の1枚です。
写真は本堂の裏手に位置する寺山風景です。西側(写真下)は広葉樹も多く、かなり色づいています。今日は日中久しぶりにサルが出没しましたから、今年もまた、餌不足が始まっているのでしょうか。
サルだけでなく、人間社会も大変です。経済の冷え込みは相当のようです。そして、何も歳末と時を合わせなくてもよいのに、ドバイショックによる円高の影響は想像以上のようであり、輸出企業の多くがアメリカ発のリーマンショックからまだ充分立ち直れていない矢先だけに「泣きっ面に蜂」といった心境かと察します。でも、いずれ近いうちにその影響が国民生活全体に及ぶのではないかと心配です。
サルやチンパンジーは生物の発達史の上で、私ども人間にかなり近い存在ですが、彼らは人間のように互いに顔を見せ合って共に食事を取ることができないそうです。そして、(親子間の感情は別として)他者を思いやる気持ちは人間特有の感情のようです。都会では救世軍恒例の社会鍋も始まっていることでしょう。仏教では、他者のために行う善い行為(相手に笑顔を見せることなども含めて)を、すべて『布施』と呼んで、尊い行為(菩薩道)の一つに位置づけています。この意味で、恒例の歳末助け合い運動なども当然の事ながら、りっぱな布施行為と言えるかと思います。
時節柄、ご自愛ください。
|
 |
 |
|
|
| 2009年11月17日(火) |
| 一雨ごとに寒くなってきました。 |
|
11月も半ばを過ぎ、肌寒い雨の日が続いています。昔だったら一雨ごとに秋が深まるというところでしょうが、季節はもう初冬です。テレビではさかんに各地の紅葉の名所が紹介されています、私どもの所(伊賀)はこれからといった感がします。
浄土宗を開かれた法然上人は、時節ごとにご自身の心境を歌に託して詠まれておられますが、その秋のお歌に「阿弥陀仏に染むる心の色に出(い)でば 秋の梢(こずえ)のたぐいならまし」とあります。阿弥陀仏のご本願に深く帰依し信ずるご自身の心を、赤く色づいた紅葉にたとえて詠まれていらっしゃるのです。
これは、当然のことながら、一朝一夕その場限りの信仰心などで赤く染まるというのではなく、年月をかけて日々仏さま(阿弥陀仏)のご本願に帰依し感謝のお念仏をお称えしていると、その結果として如来様から頂いた何とも言えない功徳(くどく)で、身も心も「その喜びの姿」に変わり、それはまるで秋の深まりにより一段と燃え立つように赤く染まる梢のようだと譬えられたのであります。
本来、仏教では私ども人間は無限の過去からの無数の体験(善い事も悪い事もそして普通のことも含めて)をして、それらの多くはいったんは忘れられるものの、そのすべてが業(ごう)としてそれぞれの『無意識の世界』にしまわれ永遠に蓄えられると言います。そして、それらの影響を毎日しかも時々刻々と受けながら、四苦八苦してこの現実社会を生きざるを得ない私たちの日常であると説きます。そして、だからこそ、このお歌の心境のように、限られた人生の中で仏さまとの出会いの機会をさまざまな方法(私ども浄土教信者の場合は「お念仏」となりますが)を通じてもつことが大切であるとお釈迦さまはおっしゃっておられるのです。
|
|
|
|
|
| 2009年11月2日(月) |
| 寺参道入り口付近に新しいお店がオープンしました! |
|
11月に入り、ずい分冷えてまいりました。昔から霜月と呼ぶはずです。当地でも今日の午後は15〜16度でした。
地方経済の停滞が話題になって久しいですが、伊賀地方でもあちこちで古い店の閉店があいつぐ中、当寺の参道入り口付近にこんな変わったお店(オーナーは壇徒M氏)が登場しました。とても明るいニュースだと思えるので本欄でご紹介させていただきます。
写真上に並んだ2棟のうち、向かって右側に位置する民家風の建物がそうです。停まっている車はオープンを前にした運搬車ですが、駐車場は道路向こうにあり約10台分のスペースがあります。いずれも商店の跡地を整備して建てられたものです。入り口左には、ケヤキ造りのりっぱな看板が掲げられていますが、内容は「大和街道」と「徳永寺縁起」についてのものです。後者については私もその本文作りに協力させていただきました。もっとも題字等はオーナのアイディアです。
店内はすべて、木彫家具づくしであり、特に中央の大テーブルは圧巻です。今回は著名な書道家さんの作品がたくさん展示されていますが、今後、期間を定めていろいろな作品が展示される予定だそうですからこれからの企画が楽しみです。もっとも、ここは軽食を中心とした和風レストランです。格調の高い作品を前に食事をされるのもいかがでしょうか。徳永寺は観光寺院ではないので、何もお見せできるものがなく申し訳ないですが、近くにこんなお店ができるのは嬉しいかぎりです。また、よろしければ、寺へお立ち寄りの際はどうぞ利用してあげてくださいね。
おっと、ご紹介が遅れました。店の名前は、「柚子霧の路」(ゆずぎりのみち)でした。よろしく!
|
 |
 |
|
|
| 2009年10月19日(月) |
| 浄土宗関東大本山への参拝旅行に行って参りました。 |
去る16日〜17日の2日間、浄土宗の関東地方の2つの大本山である東京・増上寺と鎌倉光明寺を檀信徒の皆さん30数名と参拝してまいりました。
平成15年初冬に五重相伝を受けられた方々が中心なのですが、法然上人二十五霊場参りに始まり、その後全国の大本山めぐりと足掛け6年かかりましたが、ようやくこれで無事満行です。
写真(上)の増上寺の後ろには東京タワーが見えていますが、このタワーも隣のホテル(今回の宿泊場所)も共に戦争で空襲に合う以前はすべて増上寺の境内地でした。首都のど真ん中に、こんなに広大な寺院があることが皆さんとても不思議であったようです。そして、50年ぶりにお化粧直しされたタワーの夜景にも大いに満足された様子でした。
2日めに参拝した鎌倉光明寺は、浄土宗第3祖良忠上人が開かれたお寺ですが、写真(下)は職員の方から三門の説明を伺っているところです。この門の向こうには徒歩数分で有名な湘南海岸が展開しています。当日は執事長さまに法要の導師をしていただき、その後の法話の中で、光明寺の第86世察誉貞瑞上人が小僧時代に伊賀の徳永寺に修行された方だということに触れられたので、皆さん大変感激されていました。
帰り途中には、静岡の焼津さかなセンターに寄りましたが、皆さん新鮮な魚に目を輝かせ、わずかな時間でしたが「おみやげ買い」に夢中でした。
|
 |
 |
|
|
| 2009年10月4日(日) |
| 徳永寺「山号額」の由来 |
|
カレンダーも今月に入り、残り3枚です。朝夕すっかり秋らしくなってまいりました。今回は、徳永寺本堂の正面高く掲げられている「山号額」についてお話させていただきます。
古来より、お寺にはいわゆる寺号の他に、山号・院号という名前が付けられています。当山の場合は「平庸山無量寿院徳永寺」というのが正式名称です。ちなみに京都市内にある私どもの浄土宗総本山、知恩院の場合は、「華頂山知恩教院大谷寺」というのが正式な名前なのですが、院号である「知恩院」の方が有名になってしまい、現在までそのように呼ばれています。
当山の山号であるこの「平庸」(へいよう)という言葉についてもいろいろと調べてみたのですが、今のところ辞書には見当たりません。おそらく、この2個の漢字の字義からして今、現代の日本人に最も求められていると言われる「バランス感覚」をさすのではないだろうかなぁと自分なりに思っています。そんな訳で私はこの名前が大変気に入っています。もし皆さんの中で、的確な意味をご存知であればぜひご教示願いたいところです。
また、この額(写真)の中に書かれた墨蹟は、察誉貞瑞上人というお方によるものです。この方は尾張出身で青年時代縁あって当寺で修行なされ、関東の寺院住職になられた後、最晩年、知恩院第66代管長(大僧正)に就任されたお方です。(1827〜1831) 当山には、この他、境内塀の内側に察誉上人の名号石(自然石表面に南無阿弥陀仏を彫られたもの)が建てられています。当寺へお越しの際にはぜひご覧ください。また、察誉貞瑞上人が書かれた「一枚起請文」を拝見したことがありますが、心温かいお人柄が偲ばれるとても柔らかな筆づかいでした。
|
 |
|
|
|
| 2009年9月18日(金) |
| 秋彼岸前のお化粧直しです。 |
|
寺にとってまた忙しい季節が始まります。20日からのお彼岸に備え、今日は朝から私が歴代上人墓周囲を、総代さんたちが山門前周辺をそれぞれ草刈機などで大掃除をしました。おかげさまで今のところは写真のようにたいへん美しく仕上がりました。これで秋彼岸を迎えることができます。
ところで、先週のある日の午後、とても心温まる光景に接することができました。それは、檀家のある高齢の女性の葬儀の時のことでした。私どもの周囲ではまだ自宅葬がかなり行われています。また、土葬の習慣も残っているのですが、その場合は親族を中心とした野辺送りを行い街道筋を行列をして最後のお見送りをみんなで行う良き伝統が今日も続いています。
当然私は導師として、その行列の中央辺りに位置していたのですが、遊び帰りの小学生の女の子数名が自転車を止め、商店の前でじっと合掌しているではありませんか!「今どき・・・」という感じでとても爽やかな感動的なシーンでした。
全国で凶悪な事件が次々と起こり、「命の尊さ」が叫ばれるようになってすでに久しいですが、まだまだ日本も捨てたものでもないと実感しました。後で聞くと参加者のほとんどが同じ気持ちだったようです。きっと大人たちの真摯な態度が彼女たちの素直な心を揺り動かしたのでしょう。
|
 |
 |
|
|
| 2009年9月2日(水) |
| 夏の終わりに |
|
朝夕の風からすると、ようやく夏の暑さも一段落のようです。特に、今期は衆議院選挙期間と重なったこともあり、やはり一昨夜が季節の変わり目のような感じがしました。当落の結果によって候補者の皆さんの思いはさまざまでしょうが、本当にお疲れさまでした。
あれだけ長い運動期間だったわりに、結果の判明は驚くほど速かったでした。世界には大統領選挙が行われて2週間も経つのに選挙結果がいまだに出ず新大統領が決まらない国もありますが、今回の選挙はまさにスピード社会の象徴のようです。
自民党の敗因はこんなに選挙制度が発達した国で、国政選挙を1回もしないまま4人も総理大臣を変えつないできたという「無自覚さ」と同じ政権が半世紀以上続いたことで、その金属疲労に伴う各種の弊害に多くの国民がほとほと愛想がつきたということが大きかったのでしょう。したがって、マニュフェストをテコに民主党が支持拡大をした結果ということではないと思います。
今回の敗北を通じて、初めて権力から離れた自民党の方々には結党当初の初心に帰った気持ちで出直してもらいたいです。特に若い議員さん方に期待するところ大です。この意味で、総理経験者が4人もまだ党内にいらっしゃるというのはどうなのでしょうか。(皆さんそれぞれ相も変わらず、個性強くお口も達者なご様子ですから・・・)
また、民主党さんには,これからは「旧来の自民党的なるものとの決別」という意味で各種の修羅場が待っているはずです。そして、改革を期待する国民の監視に絶えず囲まれ、自民党以上に大変なことだと思います。ぜひとも日本の民主主義確立のために頑張ってほしいです。
いずれにせよ、政治に半世紀ぶりに日本の政治に緊張関係が戻ってきそうでで、とても意義深いことだと思います。
|
|
|
|
|
| 2009年8月19日(水) |
| 残暑お見舞い申し上げます! |
|
暦の上では立秋が過ぎて早10日ですが、まだまだ残暑厳しい毎日が続いています。
そして、これから月末までの10日間は衆議院選挙があるので、日本列島はさらにヒートアップすることでしょう。どの世論調査を見ても、今回は若者を中心に投票率がかなり上がりそうだと出ています。たいへん結構なことであり、例によって開票日の夜はテレビの開票速報に釘付けされる自分が予想されます。皆さんはいかがでしょうか?
私は、政治動向というのはとても大切な事だと思いますし、日ごろ新聞の政治面もわりと小まめに読んでいる方だと思います。しかしながら、「政治」と「宗教」というのは人々の幸せを求めるという目標は共通していますが、長年にわたって人間が求めてきたこの二つの「幸福の価値」というのは、質的にまったく別物だと思うし、またそうあるべきと考えている一人です。(政治においては、当然のことながら「経済的利益」が最優先されます。)
したがって正直言わせてもらえば、宗教者が(特定の信仰を前提に)政党を組織したり、応援したりするというのは今もって賛同できません。もちろん、それぞれの宗教者個人の政治的権利や精神的自由は保障されなければならないとは思いますが・・・。
今回、各党のマニフェストを見る限り、確かに具体的な政策が提言されているのですが、国家としての未来像といったものがまったく見えてこないのは不満です。しかしながら、たとえ不充分ではあっても、戦後64年にしてようやく民主主義国家らしく、政党が(国民にも理解できる形で)政策を対立軸として掲げて争う国政選挙が実現することはたいへん見応えがあります。その意味で30日の結果がとても楽しみです。
|
|
|
|
|
| 2009年8月2日(日) |
| いよいよ、施餓鬼モードに入りました。 |
|
今朝、8月2日早朝、お施餓鬼・お盆を前にして、在住檀家の皆さんの内で徳永寺境内に墓石を建てられている皆さん方により、年1回の大掛かりの清掃奉仕を行っていただきました。境内以外の2ヶ所の墓地でも行われました。
あいにく、作業を始めて始めて間もなく雨が本降りとなてしまい、さぞ大変であったと思います。また、各自の石碑の清掃はお互い自粛することになっており、その分生垣や雑草刈りなど境内周囲全体が見違えるようにきれいになりました。おかげさまでこれでようやく、この夏も(天候は今ひとつですが・・・)さっぱりした気持ちでお施餓鬼やお盆を迎えることができます。
ところで、お施餓鬼やお盆といった夏の仏教行事は結局何のためにあるのでしょうか?
それは、結局「生者と死者との縁を改めて結び、共に仏に救われることを願うことにある。」ということに尽きるかと思います。どうか皆さんも、時には気持ちの上で、このような原点に立ち返ってこれらの諸行事にご参加されてみてはいかがでしょうか。きっと充実感が得られると思いますよ。
|
 |
 |
|
|
| 2009年7月16日(木) |
| 今年も、朝参り会が盛況にできました。 |
|
先日(11日)の朝参り会の風景2コマです。日程上、近くの方々しか参加できないと思いますが、今年もたくさんの人々がお見えになられました。天候にも恵まれ、おかげさまでとても良い雰囲気で会が進行しました。
朝6時きっかりに始めるというのは、当山の諸行事の中でも異例のものですが、それだけに参加された方々はどなたも真剣かつ熱心にお勤め(別時念仏と聞法)をなされていました。
朝がゆ
終わってみんなで一緒に和気あいあいと「おかゆ」を頂きました。「今年は時間の都合上、おかゆの出来上がり状態がうまくいきました。」とは台所担当者の弁です。おかゆ作りというのは簡単そうであって、ゆで具合が難しいようです。もっとも、五分・七分というように個人差による好きずきもありますが・・・。
お念仏
何と言ってもこれが一番大事です。何故なら、仏さまのみ名をお呼びするという、私たち衆生にとって最も尊い行為だからです。
法話
いつもながら、納得してもらえるような内容ではありませんでしたが、とにかく私なりに努めて法然上人のお念仏の特色を以下の5つに分けてお話させていただきました。(・大慈悲の教え・実践重視と平等救済の教え・純粋な教え・内省と仰信の教え・日常生活重視の教え)以上ですが、もしこれらについて、具体的な内容を知りたいと思われる方は直接メールでおたずねください。)お答えさせていただきます。
|
 |
 |
|
|
| 2009年7月1日(水) |
| 当山ホームページ「故郷百景」を更新してみました。 |
当山のhp創設当初より、徳永寺の概観等の写真をご紹介するにとどめていました「故郷百景」を、本来のタイトル名に見合うように、当地(三重県伊賀市柘植地区 旧地名;上柘植)内の主な施設などの写真を掲載させていただきました。
特に、当地のご出身の方は、写真をご覧になられて思わず懐かしんだり、ずい分変わったなぁと思われることと思います。
伊賀上野までの国道沿いに次々と大型店が進出し、ご多分に漏れず、この地も地元産業の衰えが気になるところです。かつて、駅弁が販売され、線路工夫さん等を含めると約200名の駅員さんが働かれたという柘植駅も今では臨時職員数名の方が交代で勤務されるまでに変わりました。
もう一度、地方は経済復興されねばならないと思いますし、いろんな意味でこのままでは日本の将来がダメになってしまうのではないかと危惧している一人です。
来る7月11日(土)は、恒例の朝参り会の開催です。別時念仏と法話(住職担当)が中心ですが、終わって「朝がゆ」をご接待します。よろしく。(午前6時開催)
|
|
|
|
|
| 2009年6月17日(水) |
| 裏山に咲く白い花たちがとても美しいです。 |
|
いよいよ、今年もうっとうしい梅雨の季節が始まったようです。昨日当地は、とてつもないような雷雨に見舞われ驚きました。右の2枚の写真はいずれも私どもが住まいしているところからすぐ近く(歩いて数十秒)の裏山に野生状態で咲いていたホタルブクロと笹ユリです。
いずれも早朝の、彼らが元気の良い時間帯に撮ったものです。私は花のことは詳しくありませんし、最近もホタルブクロというのが提灯の明かりとホタルの明かりにかけて命名されていることを知ったほどです。赤の種類もあるようですが、当山のはすべて白ばかりで、毎年この場所に群生して咲きます。そういえば最近は本物のホタルがブームのようであり、彼らは今モテモテですね。数年前、寺の周囲の溝をU字溝で整備したのは良かったのですが、その影響で彼らがすっかり寄りつかなくなってしまいました。何事もすべてはうまくいかないものです。
下の写真の笹ユリは、山手の笹の斜面に数年ぶりにわずか1本が見事に咲いたものです。たとえ1本であっても、周囲におもねることなく、堂々としているのがとても気に入りました。この国にも、かつてはこんな人々が都会にも田舎にも居られたのではないでしょうか?今の時代、孤独に耐え切れない人の何と多いことか!それも未来を背負う若い方々にですよ。ぜひ、野に咲く一輪の笹ユリに見習ってほしいです。
|
 |
 |
|
|
| 2009年6月1日(月) |
| 百花繚乱の季節です。 |
|
早いもので今日からもう一年の半ば、6月を迎えました。そして、これまでの新緑が一層鮮やかさを増し、いよいよ百花繚乱の季節です。右の写真は寺の裏庭を角度を変えて撮影したものです。いよいよサツキが開花し始めました。これから木々の緑と赤や白の花びらが色映えることになりましょう。もっとも、美しいサツキなどには、雑草も多く寄生しており、それらの手入れがまた大変です・・・ハイ。
先週までの新型インフルエンザ騒ぎはようやく終息に向かっているようでやれやれです。日本人の生活様式や社会のしくみがこれだけ変わってしまうと(例;数百万単位の海外旅行や関東圏や近畿圏への極端な人口集中など)、この種の感染症による被害はこれからもっと出てきそうな気がしないでもないです。
ワクチンに勝ち、生き残ったウィルスたちが益々強くなる一方で、コンピューターに頼りきる人間は抵抗力が弱くなるばかりという構図ができ、まさに私たちは先行き不透明のおかしな時代に入っているのかもしれません。仏教で言う「末法」は1万年も続くというのですから、約1千年めにあたる現代などははまだまだ序の口なのかもしれません。
であったとしても、やはり上を向いて前向きに進みたいものです。皆さんはそう思いませんか?
|
 |
 |
|
|
| 2009年5月17日(日) |
| 信州善光寺ご開帳、とてもすごい賑わいでした。 |
|
|
|
| 2009年5月2日(土) |
| 季節は、もう初夏です。 |
|
新緑の若葉が美しい時期となりました。そして、日中の気温も25度前後となり、本格的な夏がもうすぐです。写真のように駐車場付近の空き地にもサツキが色鮮やかに咲き始めました。1本おきにある低木はドウダンツツジです。写真では見えないでしょうが、小さな白い花が星のように咲いており、サツキの赤とのコントラストが絶妙です。
本来なら、この時期、当山ではボタンが真っ盛りなのですが、彼らの春はほぼ10日前に完了しました。今年も本堂の阿弥陀さまへボタンのお供えは欠かしませんでしたが、地球温暖化の影響なのでしょうか、当山の花カレンダーも近年は狂いがちです。
花と言えば、5月8日の花祭りが近づいてまいりました。本来7月15日のお盆を8月にしているように、明治になってからの太陽暦採用以来、当地方では旧暦4月8日の「花祭り」を一ヶ月遅れで行っています。花祭りは、仏教の開祖お釈迦さまのお誕生を祝う祭典であり、仏生会(え)、灌仏会、降誕会とも言われます。当日は夜8時からの開会ですが、この1年に一度の甘茶かけ、そして甘茶の不思議な味に接することも参詣者の皆さんの楽しみの一つのようです。
花は仏教のあらゆる行事につきものですが、それは彼らが、「無常」や「縁起」といったお釈迦さまの尊い、み教えのシンボルだからなのです。この短いコーナーでは割愛させていただきますが、私も法話では花に譬えて、教えの一端を説明をさせていただく事が多いです。
掲示板の俳句は「甘茶佛 地を指すゆびに 玉雫(たましずく)」です。
山崎松子作
|
 |
 |
|
|
| 2009年4月16日(木) |
| 桜舞い散る季節、近刊「利休にたずねよ」を読む |
|
全国的に話題を提供してくれた桜の季節もほぼ終わろうとしています。写真上は先週、京都の観光寺院醍醐寺の桜であり、下はわが徳永寺裏庭の桜です。どうして、この時期の日本中で、桜ばかりがこんなにもてはやされるのでしょうか?多くの春の草花がうらやましく思っていることでしょうね。いろんな方々が指摘されているように、それが日本人の伝統的な美意識に基づいているのはほぼ確かなようです。
先日、知人を通じて今年の直木賞作品の「利休にたずねよ」を読む機会を得ました。よく知られている史実である、豊臣秀吉との価値観の確執により切腹に追い込まれた千利休をテーマにした400ページに及ぶ大作です。すでに読まれた方もいらっしゃるのではないかと思いますが、利休とさまざまな歴史上の人物との出会いの場を、その事件から時系列にそって遡る形で短編を綴り上げることで、彼をただ単に茶道の創始者という観点を超えて、改めて一人の日本人として評価するという構成なのですが、とても読みごたえのある作品でした。
家具や諸道具などを通じての空間的な位置関係による美意識だけでなく、謙虚さや礼儀など対人関係の中での日本人特有の美意識が利休の美学に始まるという著者山本兼一氏の主張はそれなりに説得力あるものでした。その一方で、散りゆく桜に感じる私たちの美意識を始めとして、もうすぐ始まる田植えに見られる碁盤の目のような風景に接するたびに、この美意識は、利休の時代をはるかに超えた悠久の彼方から私たち日本人に代々受け継がれてきたようにも思えます。この民族としての血というか、今風に言えばDNAそのものに起因している面も大きいように私には思えるのですが・・・・・。
|
 |
 |
|
|
| 2009年4月7日(火) |
| わたくし、住職も気分はリフレッシュしています! |
|
さまざまな生き物に新鮮な気分を呼び起こしてくれる4月です。「田舎和尚のつぶやき」をこのコーナーでご報告させていただくのも4年目に入りました。月2回という更新のペースが毎度のように遅れ気味ですが、よろしくお願い致します。
ここ数日は私住職も忙しかったでした。と申しますのは、京都にある総本山知恩院境内に設置されている「サラナ親子教室」の主幹という仕事をこの3月末で退任・退職したことによるものです。教員生活の退職直後からの約10年に亘る勤めでしたが、この間、現代の子育て事情に何らかの接点をもつことができ、とても楽しく参考になる事も大でした。写真下の建物がその施設であり、旧尼僧道場を一部改修した寺院です。毎週約50組の親子が参加し約8名のスタッフと共に宗教情操を育むことや母子共にやすらぐ機会を提供させていただく仕事をしておりました。退任を願った理由は、私なりの役目が一段落し、このあたりでいよいよ住職の仕事に専念したいと近年思ったからでした。学卒後35年目にしてようやく実現できました。ハイ
昨日は本年度の徳永寺行事予定を立ててみました。(詳しくは「行事予定」参照ください。)お寺を訪れてくれる皆さま方に少しでもご気分をリフレッシュしていただけるよう一層の充実をめざして頑張りたいと思います。そして、それこそが私にとっての「第3の社会人生活」でもあります。何とぞ、よろしくお願い申し上げます。
|
 |
 |
|
|
| 2009年3月18日(水) |
| 春彼岸3日め、明日はお中日です! |
|
17日(月)より、今年も春彼岸が始まっています。桜の開花はまだですが、これが過ぎるといよいよ世間は桜・さくらで賑やかになります。柘植あたりはと言うと、徳永寺の裏庭ではようやく紅梅・白梅が見ごろとなりました。
今年の彼岸にあたり、境内に太陽電池による時計(写真上)が3軒のお檀家さんより奉納されました。何でも10万年に1秒の狂いだそうですから正確そのものです。両面表示ですので裏側にある墓地の方からも時間を確認することができ、お墓掃除に来られている方々からもたいへん好評のようです。昔はきっと隣の鐘楼が時計の役割を果たしていたはずですが、そんなのどかな時代が過ぎ去ってからどれくらい経ったでしょうか。
前回ご紹介申し上げたように、当寺のお彼岸は春・秋共に1週間ずつ行われ、その間毎日、総代さんたちが寺に出勤してくれます。そして、一日はまず、善光寺如来の「のぼり」を山門前に立てることから始まります。全長約7メートルほどある大きなものですから、4〜5人かかりでようやく立てることができるほど大変な作業です。
|
 |
 |
|
|
| 2009年3月4日(水) |
| もうすぐ、春彼岸です! |
|
今日あたりから、天気予報では恒例の桜の開花予報が始まりました。何でも、四国・九州地方では今月15日頃より開花が見られるとのことでした。
そして、お寺の方では春のお彼岸シーズンが始まります。以前にもお伝えしたかも知れませんが、当寺では柘植善光寺としてちょうど一週間にわたり一光三尊阿弥陀如来前にて勤行や法要を勤めます。この間、各総代さんたちも連日早朝から当寺に詰め、夕暮れ時まで寺のさまざまな業務にたずさわってくれます。住職として、これほど力強いことはなく、その分こちらは地元や各地の檀信徒の皆様から依頼されたご回向を中心に法要を勤めさせていただきます。
夕食時には、台所のお手伝いとして二人の女性にお世話になり10数人での食事を頂くことになっています。これがまたとても楽しく、春秋共に時期的に大相撲の中継と重なることでテレビ解説者顔負けの批評に接することができます。
そして、少々のお酒が入ることもあって、「寺院のあり方」についてまで前向きに話が展開することもしばしばあり、その続きは翌日となります。もう百年以上も続いている徳永寺の古くて新しい良き伝統であると住職はいつもながら思っている次第です。
|
|
|
|
|
| 2009年2月18日(水) |
| 近況報告その1 ー善光寺堂の裏に「お手洗い」を新設中ですー |
|
2月になり、温かい陽気が続くなぁと感心していたのですが、半ば過ぎより再び寒波襲来となりました。そう言えば、昨年の2月頃も当地では大雪の日が多かったでした。
話題変わって、徳永寺では現在、善光寺堂の裏に新しくお手洗いを新設中です。これが完成すると、本堂でのお参りの際などに正面階段を降りることなく直接お手洗いに行けるようになりますから、ご高齢の方はもちろんのこと、多くの方々に大変喜ばれることと思います。
俳人芭蕉は有名な「不易流行」(ふえきりゅうこう)という言葉を後世の者に残してくれました。永遠に変わらぬ本質「不易」と時々に変化する様相「流行」を意味する言葉ですが、芭蕉は人間の社会にはこの2つが共に必要だと言っています。そして、私は現代の寺院もこの精神が発揮されるべき空間の一つだと思っています。少し大層な言い方をしましたが、本堂近くに不浄な場所を設けても、そのことで一層お寺参りが盛んになれば仏さまにも喜んでいただけるのではないでしょうか?
もっとも、建設には多額の費用がかかるのは当然であり、現在檀信徒の皆様方にご寄付を募っているところです。総代会の決議を経て工事はすでに発注させていただきました。よろしくお願い申し上げます。
|
 |
|
|
|
| 2009年2月2日(月) |
| 喰ってねて 牛になりたや 桃の花 与謝蕪村 |
|
平成21年になって、早1ヶ月が過ぎました。一昨日、当山の毘沙門天初寅祭の会式(えしき)にあたり、お供え用の花を求めていたら、花屋さんの店先にも淡いピンク色の桃の花が蕾(つぼみ)ながらも出回っており早速購入した次第です。いよいよ立春ですね。
当山では毎年1月末の土曜日に秘仏「毘沙門天王像」のご開帳を行い、この1年の無事を一同でお願いします。現在善光寺堂でお祀りしている毘沙門天は、東隣の都美恵(つみえ)神社の前身として明治初期まであった旧石照院における3体のご本尊なのですが、当時の神仏分離令政策の影響を受けて廃寺となり、柘植地区内の3ヶ寺の寺院に分散して祀られ今日に至っています。しかしながら、現在も会式として法要を勤めているのは当山だけのようです。
最近あちこちで仏像の盗難被害が多くなっている関係で、写真を含めてあまり詳しい説明をできないのが残念ですが、刀八毘沙門天(とうはつびしゃもんてん)と言うのが正式のお名前で、虎にまたがり8本の刀を振りかざしておられる御姿は凛々しくとても勇壮です。近年、特に緩みきった私ども日本人の心をさぞや嘆いておられるのではないでしょうか。
当日は厄年の方々を含めて、計75名ほどの老若男女の皆さんがお集まりになられました。肌寒い天候でしたが、狭い堂内は熱気でムンムンするくらいでした。やはり、信仰心というのは有り難いものだと感心しました。この信仰心というものが有るのと無いのではおそらくそれぞれの人の心の在りようという点でかなりの差が出てきて当然かなぁと今更ながら思いました。
会式には、当寺に係わる上町、下町の両区長さんも参加されていましたが、今の時代、難しいことなのかも知れませんが、地域(コミュニティー)を代表される方々がこのような宗教的な場に居合わせていただくと、不思議と意図せずして地域全体に平和な雰囲気が醸し出されるということを改めて実感しました。実際、こういう光景が身の周りから少しずつ消えつつあるというのが、今の日本の現実なのではないでしょうか。
日本中が極貧の中にあった蕪村の時代が伺える俳句です。それにしても牛と違って、人間は昼間から寝ている訳にはいきません。そして、ピンク色に映える桃の木立とおそらく一頭であろう牛の黒さやあたりの静けさとが絶妙にこちらにも伝わってきますね。
|
|
|
|
|
| 2009年1月17日(土) |
| ただ今、寒行『托鉢行』の真っ最中です。 |
|
黒衣に網代笠(あじろがさ)の僧たちによる冬季柘植地区の風物詩、9ヶ寺の寺院僧侶による托鉢風景の一コマです。
地区内約1,000戸の家庭をお訪ねし、その際に貴重な浄財を頂いております。写真は本日17日午前中に行われた、名阪道路沿いの在所、上村地区を回っている様子ですが、それぞれのお家では縁側の戸をできるだけ開放し、お仏壇にロウソクを灯して私どもを待っていてくれます。もうかれこれ70年以上前から続く伝統行事です。
私どもは浄財を頂く代わりに、「財法二施功徳 無量檀波羅蜜 具足円満 乃至法界 平等利益」(ざいほうにせどく むりょうだんぱらみつ ぐそくえんまん ないしほうかい びょうどうりやく)というお経を称えます。つまりそこには、各施主さまから寄進である財施を頂くのに対し、私たち僧からは仏法を通しての施し(法施)をさせていただき、この二つの施しが相互に交流されることにより、「どうかこの1年、平等に幸せ(利益)になっていただきますように」という願いの意味がこめられています。
そして、これらの浄財はこの一年間の柘植仏教会活動計画にある、子ども達の花祭りや病人の方々へのお見舞い(お花)、仏教講演会、機関誌(法悦)の発行等の仏教会のさまざまな行事の活動資金として使われています。
いずれにしても、超宗派の活動であり、それぞれの仕事を持ちながら、こんなに長く続けられた続けられたことには、先輩諸師方の大きな努力のおかげだと思います。なお、当山の托鉢は来月14日(土)午前・午後です。在住の皆さま方、どうかよろしく!
|
 |
|
|
|
|
|
| 2009年1月2日(金) |
| 新年あけましておめでとうございます! |
|
新しい1年が始まりました。本年もよろしくお願い申し上げます。大晦日の除夜の鐘撞きには、今年もたくさんの方々がお越しになられ賑わいました。今年は撞き終えた後に「百八煩悩 清浄祈願 ○番」という番号札を例年の般若湯(はんにゃとう)やお菓子以外にお配りしました。来年はこの番号札を使って福引でもしてみようかなぁと思ったりしています。檀家以外の方も大いに歓迎ですのでどうぞお気軽に!
今年はアメリカも日本でも、それなりの変化をみんなが期待しているようです。因みに徳永寺には昨秋、2つの変化がありました。右の写真をご覧ください。お寺の参道入り口付近ですが、ずいぶんと広くなったと思いませんか。今まで狭くて大変だったと思いますが、諸事情を縁としてこの際拡幅させていただきました。これで車2台が対向できるようになりました。なお、正面に見えるのが徳永寺本堂の屋根です。今までは約半分しか見えませんでした。もう1つの変化は遺族会会員のお力でようやく英霊石碑群の改修ができました。約60年ぶりの快挙だと思います。お墓のことだから写真にはしませんでしたが、英霊の方々もさぞやお喜びのことだと思います。
年末よりマスコミ等で「変化」ということが論じられておりますが、仏教では「諸行無常」と言って人や物は時々刻々と変化し続けており、むしろ、この変化に気づかない所に苦悩や煩悩が起きると説きます。言わば、お釈迦さまのみ教えの根幹となっているのが「無常」ということなのです。この意味では別に意識しなくても変化され続けられているのが悲しいかな、そして楽しいかな私たちなのであります。写真下は正月2日め、寒空の下での霊山です。
どうか皆さまお互いに良き1年となりますように!
|
 |
 |
|
|