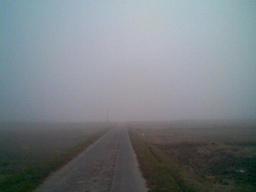モモンガのバイオリン奮戦記〜カントリーロードへの道〜(2006/11/1〜) 
(〜2006/4/30) (2006/5/1〜31) (2006/6/1〜29) (2006/7/1〜30) (2006/8/1〜31) (2006/9/1〜30) (2006/10/1〜31) HOMEに戻る
|
日記 |
||
|
2006年11月19日 |
午前中、レッスン。午後田舎の仕事。レッスンは、6つの宿題のうち、3つが合格。5割だ。それと、レッスンの始まりに、いつも先生に音を合わせてもらう(チュニングしてもらう)が、その時、「メンテナンスがいいですね」と言われた。先日、東京で調整してもらったことを話す。納得されていた。 曲は複雑になっていく。(写真は、春に向けて、耕されたたんぼ) |
|
|
2006年11月18日 |
土曜日だが、午後仕事が入っていたので、夜の帰宅となる。 練習は20分ほどする。何とか、30分、できれば、1時間は練習したい。時間をつくる努力をしよう。幸い?今は、何か資格を取るための勉強の予定はない。 先日、東京に出張の際、バイオリンを2台持っていく。1台は調整のため、1台は売るために持っていく。 調整のほうは、ていねいに見てくれて、いろいろ、教えてくれた。調整してくれるのは外人の方で英語で話されるので、店長さんが間に入ってくれて教えてくれた。駒の頭を少し削るのと、あごあてのぐらつきを直してもらうことになり、私の仕事が終わる夕方まで預けることになる。 売るために持っていった1台は、値段の折り合いがつかず、持って帰ることになった。いい楽器なので、納得のいく値段で引き取られるまで大事にしようと思う。(ずっと、手元に残りそうだ) 調整してもらった楽器で今日練習する。弦と楽器の隙間がせまくなり、押えやすくなったのと、音が確かに変わった。前と今とどちらがいいとは、わからないが、音が落ち着いて、これから、いい音を出すぞーという感じがする。楽器がそういっているような気がする。 (写真は、一度、ご紹介したかもしれないが、インターネットからいただいた写真。牛やニワトリなどがいるなかで、お母さんらしき人がバイオリンを弾いている風景。当時(といってもいつの頃が知らないが)一家に一台ではなく、一人に一台バイオリンを持っていた時代があったという。(日本のことではありません。しかし、私の母方のおじいさんは趣味でバイオリンを弾いていたらしい。)この写真は私のバイオリンの原風景です。) |
|
|
2006年11月14日 |
仕事の都合で車に乗って職場に行く。それで、帰宅途中、島村楽器による。久しぶりだった。3ヶ月ぶりくらい。それでも、顔見知りの店員さんと話したり、「弦楽ファン」という雑誌を買ったり、「アコギ・ソロ達人になれる本」という嬉しいタイトルのギターの本を買ったりした。 店員さんは、どうですか?と楽器の上達具合を心配してくれるが、キィボードとバイオリンを練習していることを、店員さんも知っているので、どちらのことを聞いているのかわからず、「まぁ、ぼちぼち」と訳のわからない返事をする。 店員さんの一人と、キィボードとパソコンをつなげるケーブルのことを話す。熱心に話してくれたが、パソコンにつないで、録音したり編集したりするのにケーブルだけでなくソフトも購入しないといけないらしく、それが7千円から2万円(幅があるが・・・)位するとのことで、そっこく、あきらめる。 こんな道草をしていたから、娘の迎えに遅れてしまい、平謝り。 帰宅後、食事の後、練習する。もちろん、バイオリンの練習。ギターも少しする。キィボードも少しする。どれも、やっぱり、ものになりそうにない。しかし、テキストは3種類、そろった。それが、嬉しい。(写真は、12日の写真と前後になったが、職場の近くの畑。野菜ができるまでの、土つくりから、愛情が注がれている。) |
|
|
2006年11月13日 |
帰宅して、夕食後練習する。少し気合を入れて、40分ほど練習する。とにかく、弾く。とにかく弾く。とにかく弾く。 宿題の曲は、先生が一度弾いただけなので、覚えられない。テキストの曲が入ったCDがあればいいが、1枚4000円〜5000円するようで、手が出ない。とにかく、音を拾いながら、音をつないでいくしかない。心を込めて、心が伝わるように弾きたいが、それ以前の問題で立ち往生。 それでも、とにかく弾いて、変化を待とう? 今、スタッカートの練習をしている。「短く切って弾く」という弾き方。それらしく、弾こうとするが、それらしく聞こえない。 (写真も、私も、五里霧中) |
|
|
2006年11月12日 |
昨日は、土曜日だが夕方まで仕事で、帰宅は9時前。1時間ほど帰る電車の時間待ちのため、立ち飲み屋に寄っていた。目的は時間待ちか立ち飲み屋か、難しいところ。 帰ってから、食事をして、練習する。20分ほど。だんだん、気合が弱まってきて、30分続かなくなってきた。 今日は、父親の17回忌。親戚は、車で来てくれたので、お酒はなし。夜、30分ほど練習する。気合が戻ってきた。 「練習すれば、上手くなりそうな気がする」と10日に書いたが、今日は、練習しても上手くなりそうにない気がした。集中して練習するが、同じところで同じように間違うし、上手く弾けない。う〜ん、難しいから、面白い。そう、今日はこれでいこう。 ギタリストの押尾コウタロウが右手の爪を伸ばしていたので、爪を伸ばせば上手くなると思い込んだ私は、ひたすら爪を伸ばした。そのたびに、手入れが悪いのか、もともと、無理があるのか、少しものにあたると、爪が欠けた。昨日もそうで、結局、右の爪を少し長め、程度にやすりで整えた。それで、爪を伸ばしている間は中断していたキィボードを久しぶりに弾いた。図書館で「楽譜が苦手なお父さんのためのもっとやさしいピアノ塾」という、これでもかという感じの本を借りてきて、練習を始めた。それでも、やさしくないと感じる私は、何だろう?(写真は、職場の近くにあるいつもの?畑。見るのが楽しみな畑です。) |
|
|
2006年11月10日 |
帰ってから、お約束どおり、30分練習する。とにかく続けること。気合は続く。 練習すれば、うまくなりそうな気がする。この楽観的見通しが、自らを助け、時に計算違いを引き起こす。いや、よく計算違いを引き起こす。今は、同じ曲を何度も何度も繰り返すのみだ。 そして、楽しく弾くこと。弾くことを楽しむこと。これに、徹したい。(写真は朝、見つけた西の月) |
|
|
2006年11月8日 |
1時間くらい練習する。このくらいやると、満足感がある。内容はともかく、時間に満足? そう、この1年間は1日10分とか、15分とかの練習時間で、1年間で12ページしか進まなかった。1日1時間やれば、5倍くらいは早く進むか? そんなことはないか。 しかし、せめて、1日30分は練習したい。なにせ、能力的には頭も筋力も神経も下降しているのだから、毎日やらないと、維持・あわよくば向上はおぼつかない、と気合を入れる今日この頃。(写真はただの月。) |
|
|
2006年11月7日 |
朝から仕事があわただしく、午後も、病院訪問など落ち着かなかった。帰宅は9時前。夕食の後、練習する。30分ほどする。 毎日練習する、というのが大事と考え、努力しているが、なかなか進歩を実感することはできない。しかし、たぶん、ほんの少しずつ、上手になっていると思う。たぶん・・・。 去年の今頃は、今使っている教本の16ページあたりを練習していた。今、28ページあたりなので、1年で、12ページ。ちょうど、1ヶ月で1ページというペースで、これは、大変だ。今使っている教本は2巻目で47ページまである。予定では、(あくまでも自分のだが、)今年度で2巻目は終了し、来年度は、晴れて3巻目突入をもくろんでいたが、そうなると、今年度の残り5ヶ月は、1ヶ月4ページのペースでないと終わらない。無理だ。 今のペースだと、2巻目を終わるのが、あと、20ヶ月。ということは1年と8ヶ月。・・・・・・・・・・。悲しい。(写真は、ごぞんじ、セイタカ アワダチソウ。全国に広がっている。昨日の写真の花が、こんなに、大きくなるとは。) |
|
|
2006年11月6日 |
11月も6日が過ぎた。早い。この間に地域の行事=スポーツフェスティバルがあって、体育委員としてバレーボールの付き添いをした。行事も、一つひとつ終わっていく。しっかり、打ち上げにも参加させてもらう。 という中で、練習もやる。さすがに、お酒が入った日は無理だが、それでも、音だけは出そうとする。涙ぐましいが、成果にはつながらない。 今日も、しっかり練習する。私なりのしっかりなので、あてにはならない。22分くらい、練習する。新しい宿題の曲が、なんとなく、曲らしくなってきた。「ガボット」という曲。“という曲”といっても、ネットで見たら、「ガボット」という曲は、バッハなども書いている。練習曲は、コレルリという人の曲。(写真は、セイタカ アワダチソウ。これくらいの時は、かわいい花だが・・・) |
|
|
2006年11月1日 |
練習を10分ほどやる。申し訳程度にやる。とにかく、音を出したという、なんというか、そういうこと・・。新しい宿題の曲にチャレンジしている。一度、この前のレッスンで先生の演奏を聴いている。曲の雰囲気はなんとなく覚えているが、おたまじゃくしが読みとれない。 それでも、何とかなるだろうと思ってしまうのが、こわい。 (写真は、朝の犬の散歩の時の風景。朝の寒さと昼の暖かさの差が大きいのか、もともと、霧の多い土地ではあるが。「朝霧は晴れ」 |
|
(〜2006/4/30) (2006/5/1〜31) (2006/6/1〜29) (2006/7/1〜30) (2006/8/1〜31) (2006/9/1〜30) (2006/10/1〜31) HOMEに戻る