 |
| HOME
> 伊賀上野芭蕉史跡ガイド > ふるさと芭蕉の森公園 |
|
 |
|
 |
| ■ ふるさと芭蕉の森公園 |
|
昭和63年(1988)から平成元年(1989)にかけて、特色を生かした地域づくりを行う「ふるさと創成事業」により、上野市が市民の方からアイデアを募集し整備した。平成2年8月に完成し、芭蕉句碑が十基建てられた。この上野市の新名所は憩いと散策の場として人々に親しまれています。 |
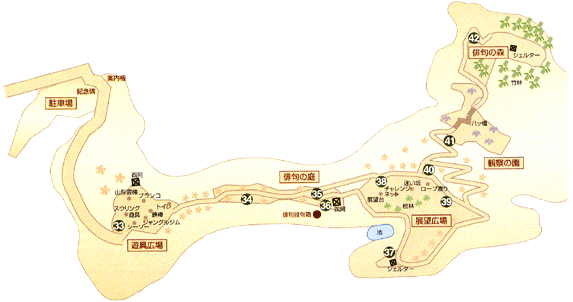 |
| >>地図の拡大図はこちら |
 |
| 33. 雲とへだつ 友かや雁の 生きわかれ |
|
|
|
【遊具広場】
寛文12年(1672)春の作。季語は「帰雁」。俳諧師を志し江戸に下る際の留別の句とも伝わる。
| (句意)雲のように遠く隔たって行き別れになってしまう友なのか。北国の空に去りゆくあの雁たちは。だが仮の生き別れだ。また会える日もあろう。 |
|
|
 |
| 34. 野ざらしを 心に風の しむ身かな |
|
|
|
【俳句の庭】
貞亨元年(1684)秋の作。季語は「身にしむ」。『野ざらし紀行』の旅の出立吟。
| (句意)旅の途中で行き倒れて野晒しの白骨となる覚悟で、いざ出立しようとすると、ただでさえ肌寒く物悲し秋風が、いっそう深くしみるわが身だ。
|
|
|
 |
| 35. 古池や 蛙飛びこむ 水の音 |
|
| |
貞享3年(1686)春の作。季語は「蛙」。古池の位置づけはないが江戸深川の芭蕉庵の傍と解される。芭蕉の代表作であるこの句は、蕉風展開の句として閑寂幽玄の句風を打ちたてる基になった。
| (句意)春日遅々たる春の昼下がり。水の淀んだ古池は森閑と静まり返っている。と、一瞬、ポチャッと蛙の飛びこむ水音がして、あとは再びもとの静寂。
|
|
|
 |
| 36. 旅人と 我名よばれん 初しぐれ |
|
|
貞亨4年(1687)冬の作、『笈の小文』の旅への歓送の句会で詠む
。季語は「初しぐれ」。
| (句意)潔い初時雨にぬれながら、道々で「もうし旅のお人よ」と呼ばれる身に早くなりたいものだ。
|
|
|
 |
| 37. 俤や 姨ひとり泣く 月の友 |
|
|
【展望広場】
貞享5年(1688)秋の作。季語は「月」。中秋の名月の夜、更科での吟。
| (句意)姨捨山の月を眺めていると、月夜に捨てられてひとり泣き暮したという老婆の幻影が浮かんでくる。今宵はその面影を月見の友とすることだ。
|
|
|
 |
| 38. 行春や 鳥啼魚の 目は泪 |
|
|
元禄2年(1689)春の作。季語は「行く春」。
「おくのほそ道」旅立ちの際、見送りの人々への留別の句。
| (句意)今まさに過ぎ去ろうとする春に別れを惜しむかのように、鳥は啼き、魚は目に涙を湛えている。
|
|
|
 |
| 39. 閑さや 岩にしみ入る 蝉の聲 |
|
|
元禄2年(1689)夏の作。季語は「蝉」。『おくのほそ道』の旅中、立石寺での吟。
| (句意)全山静寂の中で、苔むした岩に滲み透るような細く澄んだ蝉の声が、いっそう静寂感を深める。
尾花沢でゆっくり休んだ芭蕉と曾良は、天気の良い27日に、清風が仕立ててくれた馬に乗って山形市山寺の宝珠山中腹にある天台宗の立石寺を昼過ぎに訪れよむ。
|
|
|
 |
| 40. 此秋は 何で年よる 雲に鳥 |
|
|
元禄7年(1694)秋の作。季語は「秋」。
| (句意)思えば多年、漂泊の旅を重ねてきたが、この秋はなんでこうも深く老いの衰えを感ずるのか。孤独な思いでふり仰ぐと、遠くはるかな雲間に消えてゆく鳥の姿が、たまらなく寂しい。
|
|
|
 |
| 41. 行秋や 手をひろげたる 栗のいが |
|
|
【観察の園】
元禄7年(1694)秋の作。季語は「行秋」と「毬栗」。伊賀での吟。
| (句意)晩秋の山道には栗の毬が大きく割れたまま梢に残っている。去り行く秋を惜しみ、手のひらをいっぱいに広げて秋を押し戻そうとでもするように。
|
|
|
 |
| 42. 旅に病んで 夢は枯野を かけ廻る |
|
|
【俳句の森】
元禄七年(1694)冬の作。季語は「枯野」。 芭蕉病中吟。
| (句意)旅先で死の床に臥しながらも、見る夢はただ、あの野この野と知らぬ枯野を駆け回る夢だ。
|
|
|
| ※なお、記載内容において、建立者及び書の揮毫者の敬称は省略させていただき、役職名は建立当時のものといたしました。 |
| ※参考、上野市・上野市教育委員会制作ガイドブック「芭蕉句碑散歩」より |
| |
 |
 |